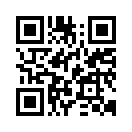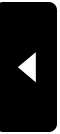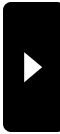2011年03月15日
東京での買いだめについて
東北地方太平洋沖地震におきまして被災された方、そのご家族・関係者の皆様には心よりお見舞い申し上げます。
転載。<ここから/>
首都圏を中心に消費者の極端な「買いだめ」が起きていることが報告され、蓮舫消費者担当相は、冷静な対応をとるよう呼びかけた。
経済産業省の担当者がスーパー大手から聞き取ったデータを紹介。
13~14日にかけて首都圏の店舗からの発注量は、水が通常の10倍、納豆が2~3倍、豆腐が1.7倍、牛乳が1.5倍に。
売上額だと、鶏肉が9倍、缶詰が3倍、大型ペットボトル飲料が1.8倍、コメ1.6倍に。食料品以外でもガスコンロの売り上げは6倍、自転車が3倍、マスクが2.5倍に。
東京都内のガソリンスタンドに客が殺到し、混乱した例も報告された。
経産省の説明では、原油は国や民間企業の備蓄などで約200日分の在庫がある。
6製油所が震災で稼働停止となり、国内の精製能力はいつもの70%に落ちたが、うち3製油所は今週から来週にかけて復旧できる見通しで、十分な供給量を確保できるとしている。
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会の宮本一子常任顧問は「消費者は、自分だけ良ければという意識を自粛してほしい。買い占めをしないといった、身の回りでできることをすることから、復興は始まる」と指摘する。
</ここまで>
私は日本人は根本、個人だとその人となりで行動し、集団だとその集団意識で行動する民族だと思っているので、上記の行動は個人の意識レベルとも言えるし、集団パニックとも言える。近所のスーパーも「物資不足により、しばらく特価セールは止めます」なんて言っちゃっているから、更にパニックに拍車をかける。
根本的に身勝手な人はさておいて、「不安・恐怖」は正確な情報を収集することで回避できる。
ただでさえ、ナチュブロをやってキャンプを趣味としている人はサバイバル意識が高い人が多いと思うし、周りからもそう思われていると思う。そんな人達が買いだめをすると、一般の人は更にパニックを起こします。
なので、東京に住む、なんちゃって野営者の私の見解を。
・基本、東京(沿岸をのぞく)は首都であり、空爆でもない限り安全。
・多少の災害でも、備蓄、災害用貯水タンク、井戸が至る所にある。
・大地震でもプレート的に今回のような津波が襲うことはない。むしろその後の火事が問題。
・日本列島の長さを考えても、列島すべてが同時災害は起こるわけもないので、物資がなくなることはない。なので、個人物資は最高でも数日ほどで問題ない(一般災害袋レベルでも可)。
・都外からの物資が届けられない災害だと、そもそも毛布さえも持って逃げることもできないレベルなので、個人物資も車も意味がない。
・上記を鑑みると、買いだめは意味がない。
なので、普段と同じ消費生活をしています。キャンプ道具の買い足しもしていないです。1回限りの燃料を毎回購入して全消費して、燃料在庫ゼロ、というわけでもないので。
賛同するキャンパーの方は、会社等、自分の周りのコミュニティーで是非お話してみてください。
せめて、周囲の人があなたのことをキャンパーと知っていたら、決して
「いや~、昨日ガススタで2時間並んでやっと灯油ゲットしたよ!」
などとは実際にやったとしても言わないこと。心の中で(この人レベルの人が準備するなら、私も準備しないと・・・・)となってしまいます。その人はまた別の人に話して、行動して・・・・
※平常心で生活するための思考方法論であり、科学的・専門学的根拠に基づいたものではありません。
※買いだめ、買い占め、常時より買い足しをしている方を誹謗中傷する意図はまったくありません。
3月16日追記 ~スーパーの状況視察を備忘録的に追記
転載。<ここから/>
首都圏を中心に消費者の極端な「買いだめ」が起きていることが報告され、蓮舫消費者担当相は、冷静な対応をとるよう呼びかけた。
経済産業省の担当者がスーパー大手から聞き取ったデータを紹介。
13~14日にかけて首都圏の店舗からの発注量は、水が通常の10倍、納豆が2~3倍、豆腐が1.7倍、牛乳が1.5倍に。
売上額だと、鶏肉が9倍、缶詰が3倍、大型ペットボトル飲料が1.8倍、コメ1.6倍に。食料品以外でもガスコンロの売り上げは6倍、自転車が3倍、マスクが2.5倍に。
東京都内のガソリンスタンドに客が殺到し、混乱した例も報告された。
経産省の説明では、原油は国や民間企業の備蓄などで約200日分の在庫がある。
6製油所が震災で稼働停止となり、国内の精製能力はいつもの70%に落ちたが、うち3製油所は今週から来週にかけて復旧できる見通しで、十分な供給量を確保できるとしている。
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会の宮本一子常任顧問は「消費者は、自分だけ良ければという意識を自粛してほしい。買い占めをしないといった、身の回りでできることをすることから、復興は始まる」と指摘する。
</ここまで>
私は日本人は根本、個人だとその人となりで行動し、集団だとその集団意識で行動する民族だと思っているので、上記の行動は個人の意識レベルとも言えるし、集団パニックとも言える。近所のスーパーも「物資不足により、しばらく特価セールは止めます」なんて言っちゃっているから、更にパニックに拍車をかける。
根本的に身勝手な人はさておいて、「不安・恐怖」は正確な情報を収集することで回避できる。
ただでさえ、ナチュブロをやってキャンプを趣味としている人はサバイバル意識が高い人が多いと思うし、周りからもそう思われていると思う。そんな人達が買いだめをすると、一般の人は更にパニックを起こします。
なので、東京に住む、なんちゃって野営者の私の見解を。
・基本、東京(沿岸をのぞく)は首都であり、空爆でもない限り安全。
・多少の災害でも、備蓄、災害用貯水タンク、井戸が至る所にある。
・大地震でもプレート的に今回のような津波が襲うことはない。むしろその後の火事が問題。
・日本列島の長さを考えても、列島すべてが同時災害は起こるわけもないので、物資がなくなることはない。なので、個人物資は最高でも数日ほどで問題ない(一般災害袋レベルでも可)。
・都外からの物資が届けられない災害だと、そもそも毛布さえも持って逃げることもできないレベルなので、個人物資も車も意味がない。
・上記を鑑みると、買いだめは意味がない。
なので、普段と同じ消費生活をしています。キャンプ道具の買い足しもしていないです。1回限りの燃料を毎回購入して全消費して、燃料在庫ゼロ、というわけでもないので。
賛同するキャンパーの方は、会社等、自分の周りのコミュニティーで是非お話してみてください。
せめて、周囲の人があなたのことをキャンパーと知っていたら、決して
「いや~、昨日ガススタで2時間並んでやっと灯油ゲットしたよ!」
などとは実際にやったとしても言わないこと。心の中で(この人レベルの人が準備するなら、私も準備しないと・・・・)となってしまいます。その人はまた別の人に話して、行動して・・・・
※平常心で生活するための思考方法論であり、科学的・専門学的根拠に基づいたものではありません。
※買いだめ、買い占め、常時より買い足しをしている方を誹謗中傷する意図はまったくありません。
3月16日追記 ~スーパーの状況視察を備忘録的に追記
3月15日状況
・西友
精肉・・・ゼロ
鮮魚・・・潤沢
野菜・・・潤沢
惣菜・・・通常通り
ティッシュ、トイレットペーパー・・・ほぼゼロ
パン・・・ゼロ
乾麺類・・・残り僅か
水・・・残り僅か
レトルトカレー・・・ゼロ
店舗内パン屋・・・半分くらいの在庫あり(なぜ?)
・近所の高級スーパー
精肉・・・通常通り
鮮魚・・・通常通り
野菜・・・通常通り
惣菜・・・通常通り
ティッシュ、トイレットペーパー・・・ほぼゼロ
パン・・・ゼロ
乾麺類・・・残り僅か
水・・・残り僅か
レトルトカレー・・・残り僅か
・近所の普通のスーパー
精肉・・・ほぼゼロ
鮮魚・・・ほぼゼロ
野菜・・・通常通り
惣菜・・・ほぼゼロ
ティッシュ、トイレットペーパー・・・ほぼゼロ
パン・・・ゼロ
乾麺類・・・残り僅か
水・・・ゼロ
レトルトカレー・・・ゼロ
とはいえ、時間帯にもよるのか、客のカゴの中身は大半は普通にみえた。
中には、「絶対に核シェルターに入るんだよね?」という以上な量の乾麺類&調味料を購入する親子もいたが・・・。
道には両手にトイレットペーパー、ティッシュ、紙オムツを下げている人は多数見受けられる。
・西友
精肉・・・ゼロ
鮮魚・・・潤沢
野菜・・・潤沢
惣菜・・・通常通り
ティッシュ、トイレットペーパー・・・ほぼゼロ
パン・・・ゼロ
乾麺類・・・残り僅か
水・・・残り僅か
レトルトカレー・・・ゼロ
店舗内パン屋・・・半分くらいの在庫あり(なぜ?)
・近所の高級スーパー
精肉・・・通常通り
鮮魚・・・通常通り
野菜・・・通常通り
惣菜・・・通常通り
ティッシュ、トイレットペーパー・・・ほぼゼロ
パン・・・ゼロ
乾麺類・・・残り僅か
水・・・残り僅か
レトルトカレー・・・残り僅か
・近所の普通のスーパー
精肉・・・ほぼゼロ
鮮魚・・・ほぼゼロ
野菜・・・通常通り
惣菜・・・ほぼゼロ
ティッシュ、トイレットペーパー・・・ほぼゼロ
パン・・・ゼロ
乾麺類・・・残り僅か
水・・・ゼロ
レトルトカレー・・・ゼロ
とはいえ、時間帯にもよるのか、客のカゴの中身は大半は普通にみえた。
中には、「絶対に核シェルターに入るんだよね?」という以上な量の乾麺類&調味料を購入する親子もいたが・・・。
道には両手にトイレットペーパー、ティッシュ、紙オムツを下げている人は多数見受けられる。
Posted by だんごまん(BETA) at 10:02│Comments(2)
│日記
この記事へのコメント
私はこれまでの人生の中で2度の震災と、大型台風の直撃、大雪を経験しました。
いずれも新潟県での被災です。
実際に被災した体験から申しますと、キャンプや野宿の経験などというのは、天地異変の自然災害にはほとんど役に立たないと思っておいたほうが無難です。
むしろ半端な知識が不測の事態を招くことすらあります。
被災地での野宿は我が身や家族の命を必死で守ろうとするがための、本人の意志に関係なく行わざるを得ない行為です。 キャンプやツーリング先での野宿のようなお遊びとは違うんです。
いくら延べ数十日を野宿で過ごしたことのある人であっても、氷点下の真っ暗闇の中で着の身着のまま避難した状態の中で、火器類もなしに濡れた木っ端に火を熾せると思いますか?
私が子供の頃に地震で避難した時は、まだ百円ライターなんかも無い時代でしたから、避難先での火熾しにはずいぶんと苦労をしたと父が話していた記憶が残っています。
また物流経路や交通機関も今ほど発達はしておらず、食糧や水の調達にはかなり大変だったとも話していました。
キャンプとサバイバルは違います。
いくらキャンプや野宿の経験が豊富といっても、それを過信してはいけません。
それらの経験はいざ被災地では、これっぽっちの役にも立ちませんから。
キャンプやツーリング野宿は不自由なく過ごすための道具と、充分な食糧があるから出来る行為なのです。
テントも寝袋も食糧も持たずに、家着のまま真冬のキャンプに出掛ける人はいますか?
もちろんいないでしょう。
ですが被災地ではそれが現実のものとなって、我が身に降りかかって来るのです。
各地で起きている物資の買いだめをする気持ちも理解出来なくもないですが、何も今すぐに日本中からガソリンや食糧、トイレットペーパーが消えて無くなるわけじゃないんですからね。
被災地の方々は食糧も暖を取る手段もない中でじっと耐えているのですから、今こうして水も電気も食糧もある我々は、せめて買いだめという愚かな行為は謹みましょう。
そしていざという時のために普段からの食糧と水の備蓄、火器 灯火器類を用意しておきましょう。
いずれも新潟県での被災です。
実際に被災した体験から申しますと、キャンプや野宿の経験などというのは、天地異変の自然災害にはほとんど役に立たないと思っておいたほうが無難です。
むしろ半端な知識が不測の事態を招くことすらあります。
被災地での野宿は我が身や家族の命を必死で守ろうとするがための、本人の意志に関係なく行わざるを得ない行為です。 キャンプやツーリング先での野宿のようなお遊びとは違うんです。
いくら延べ数十日を野宿で過ごしたことのある人であっても、氷点下の真っ暗闇の中で着の身着のまま避難した状態の中で、火器類もなしに濡れた木っ端に火を熾せると思いますか?
私が子供の頃に地震で避難した時は、まだ百円ライターなんかも無い時代でしたから、避難先での火熾しにはずいぶんと苦労をしたと父が話していた記憶が残っています。
また物流経路や交通機関も今ほど発達はしておらず、食糧や水の調達にはかなり大変だったとも話していました。
キャンプとサバイバルは違います。
いくらキャンプや野宿の経験が豊富といっても、それを過信してはいけません。
それらの経験はいざ被災地では、これっぽっちの役にも立ちませんから。
キャンプやツーリング野宿は不自由なく過ごすための道具と、充分な食糧があるから出来る行為なのです。
テントも寝袋も食糧も持たずに、家着のまま真冬のキャンプに出掛ける人はいますか?
もちろんいないでしょう。
ですが被災地ではそれが現実のものとなって、我が身に降りかかって来るのです。
各地で起きている物資の買いだめをする気持ちも理解出来なくもないですが、何も今すぐに日本中からガソリンや食糧、トイレットペーパーが消えて無くなるわけじゃないんですからね。
被災地の方々は食糧も暖を取る手段もない中でじっと耐えているのですから、今こうして水も電気も食糧もある我々は、せめて買いだめという愚かな行為は謹みましょう。
そしていざという時のために普段からの食糧と水の備蓄、火器 灯火器類を用意しておきましょう。
Posted by ナマズのひげ at 2011年03月20日 05:38
@ナマズのひげさん
こちらは個人のブログのなので、私のエントリーに関係のない持論展開は自らのメディアで発信願います。
で、私の記事に関する内容に関してコメントさせていただくと・・・。
>普段からの食糧と水の備蓄、火器 灯火器類を用意しておきましょう
多分、これが買いだめをしている人の言い訳なのだと思います。今は「普段」ではなく「非常時」ですが、ただ、今から用意して何が悪い、みたいな。
不安を煽られて行動する群衆心理の中で下手に普通の行動をすると今度は「不謹慎厨」に叩かれたりします。
難しいものです。
こちらは個人のブログのなので、私のエントリーに関係のない持論展開は自らのメディアで発信願います。
で、私の記事に関する内容に関してコメントさせていただくと・・・。
>普段からの食糧と水の備蓄、火器 灯火器類を用意しておきましょう
多分、これが買いだめをしている人の言い訳なのだと思います。今は「普段」ではなく「非常時」ですが、ただ、今から用意して何が悪い、みたいな。
不安を煽られて行動する群衆心理の中で下手に普通の行動をすると今度は「不謹慎厨」に叩かれたりします。
難しいものです。
Posted by だんごまん(BETA) at 2011年03月20日 08:53
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。